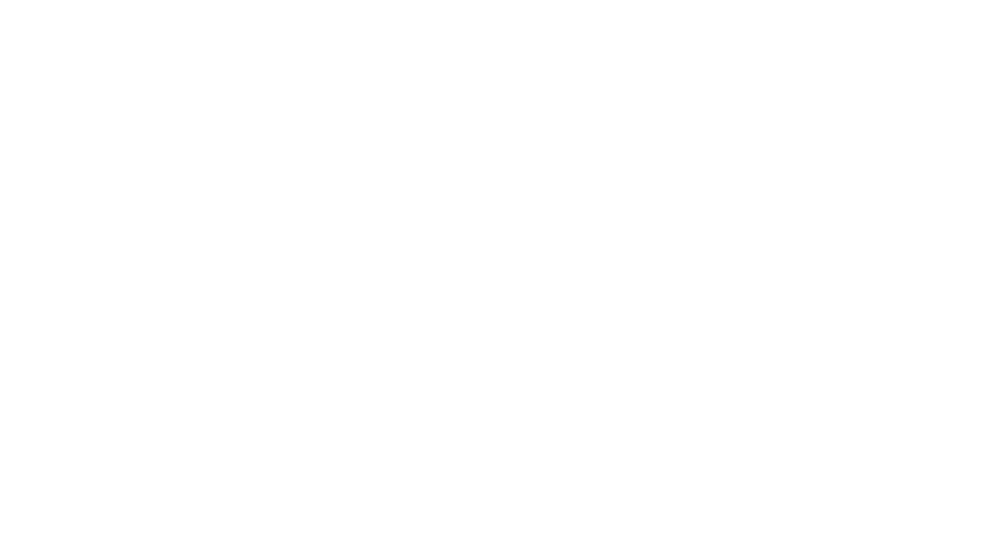あなたの暮らしを守り抜く、西崎つばさの政策
1.物価高対策・暮らしの底上げ
(1)暮らしの負担軽減
- 医療や介護、教育や保育、障がい者福祉などのベーシックサービスを抜本的に強化し、あらゆる人々の不安を解消します。
- 多死社会を見据え、公営火葬場の整備支援や、民間火葬場の利用者負担軽減を目指します。
- 水道料金の引き下げは、暑さ対策として期間限定で実施するのではなく、物価高対策、家計を応援する観点から拡充します。
(2)住まう権利を守る
- 誰ひとり取り残さない住宅支援施策として、家賃補助の仕組みを創設します。
- 投資目的の不動産購入への規制、適正な課税措置を含めた空き家・空き室対策の拡充、まちづくり制度を活用したアフォーダブル住宅の提供などを通じて、住宅事情の改善に取り組みます。
(3)所得向上・働き方改革
- 物価上昇を上回る賃上げ支援、年収の壁対策、同一価値労働同一賃金、正規雇用化の促進など、若い世代をはじめ、労働者の所得向上を図ります。
- カスハラ防止条例を活用し、従業員を守る対策を推進します。また、フリーランスやギグワーカーを含めた、多様な働き方を実現する環境整備を支援します。
- 各業界の人手不足解消に向けて、制度や設備の見直し支援および、エッセンシャルワーカーの処遇改善を進めます。
- 官製ワーキングプアをなくし、公共サービスの質向上を図る観点から、新担い手三法の実効性を高める取り組みを進めるほか、公契約条例の制定に取り組みます。
(4)産業・観光の支援
- DXや環境、シニア市場など成長分野の製品開発、海外進出や知財活用、地域ブランド創造や事業承継など、実情に合わせた支援を届けるとともに、取引適正化対策を強化し、賃上げ原資の確保を進めます。
- 持続可能な観光資源の開発や多様なMICEの推進、事業者の受入対応力向上やDXの支援と同時に、地域環境の保全やオーバーツーリズム対策を強化します。
2.医療・介護・救急体制の充実
(1)医療・介護・救急
- 都立病院における行政的医療を充実強化させるとともに、感染症や災害時に向けた体制を整えます。また、多摩地域の保健所の体制強化を図ります。
- 救急隊の増強や救急車の適正利用を進め、都民の命を守る体制を強化します。
- がん検診の受診率向上や、治療と仕事の両立支援、各種研究の推進に向けて、がん対策推進条例を制定します。
- 各種依存症について、当事者団体との連携を深めるとともに、若者のオーバードーズ対策を進めます。
(2)高齢者
- 介護基盤の整備や地域偏在解消、現場のDXや機器活用などの負担軽減、介護・フレイル予防の強化に加え、認知症患者の社会参加や理解促進、家族への支援を進めます。
- 生活機能の低下、移動困難、孤独・孤立など、高齢者の暮らしの不安の解消に取り組むとともに、就労や地域活動、生涯学習といった社会参加を支えます。
(3)コミュニティ
- 町会や自治会はもちろん、NPOなど多様な繋がりに向けた活動の支援に加え、ボランティアの育成や地域福祉との連携などを深め、地域の力を強化し、おひとりさま高齢者の対策を進めます。
3.環境・快適都市と安心のまちづくり
(1)災害から都民を守る
- マンションを含めた耐震化の促進、木密地域対策や無電柱化の推進、危険なブロック塀の除去や土砂災害対策など、住宅や地域の安全性を高めます。
- 地域の防災力・受援力の強化や、避難の判断に役立つ情報公開や啓発強化など、都民の備えを支援します。
- 災害関連死の防止に向けて、個室テント設置や温かい食事の提供、衛生的なトイレなど、人間らしい生活ができる避難所運営に向けて取り組むとともに、福祉避難所・スペースの整備を進めます。
- 帰宅困難者対策として、民間施設の確保や支援を進めます。
- 区市町村との連携や都立公園の活用を含め、災害廃棄物への万全な体制を整えます。
- 東部低地帯をはじめ、都内各地の河川や下水道、調節池の整備、流域対策など、浸水対策を進めます。
(2)犯罪の抑止、被害者支援
- 防犯カメラなどの設置に係る負担軽減に取り組むとともに、幅広い年代を対象に闇バイト対策を強化し、体感治安の向上を図ります。
- 犯罪被害者支援条例に基づき、相談体制や経済的支援の強化に取り組みます。
(3)インフラ管理
- 道路や橋梁、上下水道や河川などの整備・補修・長寿命化など、地域住民の安全を最重視したインフラ維持管理を図ります。
- 水道事業の公営を堅持しつつ、上下水道の連携強化によるサービス向上、耐震化などの防災対策を進めます。
(4)環境・気候変動対策
- 新技術の開発・活用支援など再エネ、蓄電池の普及拡大、ZEVの促進、建物の環境性能の向上とともに、デジタルも活用した気候都民会議を開催し、協働の取り組みを進めます。
- 多摩の森林や緑地の保全を進めるとともに、みどり率に加えて樹冠被覆率を指標とした都市の緑の向上を目指します。
- エシカル消費を推進するとともに、廃棄物の3Rを進めます。
- ネイチャーポジティブの考え方を進め、自然や生物多様性の保全・回復に取り組みます。
- アニマルウェルフェアの趣旨を踏まえた適正飼育の普及啓発および、動物取扱業の監視強化に取り組みます。
- PFAS対策に向けて、国と連携した米軍との協議や、地下水の調査および結果の情報公開を継続します。また、農畜産物の生産・販売への不利益が生じない対応を図ります。
(5)人が主役のまちづくり
- まちづくりにおける市民参加の充実を図り、多様なライフスタイルに対応した人中心の空間創出を目指します。
- 羽田経路の固定化回避に向けて、国への要請を継続し、同時に航空機の騒音対策を進めます。
(6)交通政策、移動の自由
- ヘルメット着用や通行空間の整備など自転車の安全利用を促進するとともに、電動キックボードやモペットの適正利用の啓発および違反の取り締まりを強化します。
- 鉄道駅へのホームドア設置加速やバリアフリー化、障害者に配慮した信号機などの環境整備を進めます。
- コミュニティバスの経費補助や各種ドライバーの確保など、公共交通維持に向けた支援を拡充します。
(7)港湾・農業
- DX推進など東京港の国際競争力を強化するとともに、気候変動の影響に備えて対策を強化します。
- ベイエリアでは、噴水よりも都民の暮らし向上に資する施策を優先し、長期的な経営計画を策定します。また、IR調査費は計上せず、カジノ誘致から撤退します。
- 地産地消の推進や農畜産物のブランド化、農業経営の多角化やスマート化など、地域の特性に則した支援を実施します。また、林業の効率化や省力化、担い手の確保、多摩産材の利用拡大などに取り組み、花粉の発生源となる森林対策にも繋げます。
4.子育て支援を世界トップレベルへ
(1)子ども・子育てを支える
- 子どもを権利の主体と捉え、最善の利益を実現するため、子ども目線に立って、その意見を各種施策に反映させます。
- 制服や学用品、行事参加費の無償化、そして受験生チャレンジ支援の所得制限撤廃や給付型奨学金の創設など、教育にかかる保護者の負担を軽減します。また、子ども医療費の完全無償化や018サポートについて、公平で効果的な事業実施を進めます。
- 待機児童・学童の解消、特に地域偏在の解消を進めながら、職員の処遇改善・質の向上にも取り組みます。
- ヤングケアラーや児童虐待対策、フリースクール支援の拡充、外国にルーツを持つ子どもたちの支援など、個々が抱える多様な課題に対応します。
- プレーパークの運営支援や公園・広場の積極活用など、子どもが主体的な遊びを通じて育つ環境を整備します。また、子ども・若者の居場所づくりを支援します。
- 子どもの事故予防や安全対策、製品開発の支援を強化し、普及に取り組みます。
(2)多様で質の高い教育
- 児童や生徒が主体的に学び、自分らしく生きる力を育む教育に向けた、ソフト・ハード両面からの充実に加え、教職員の業務の見直しや外部委託、補助・専門人材の活用といった負担軽減策を進めます。
- 併願制の検討など、都立高校の入試制度改革に取り組みます。特に、英語スピーキングテストはトラブルがあまりに多く、公平性・公正性が確保できないことから、結果の活用を中止します。
- 校内別室指導の活用や支援人材の拡充、チャレンジスクールの体制強化など、個々の事情にきめ細かく応じ、学びを止めない体制を構築します。
- 私立中学校の奨学金、高校も含めた入学金や施設費などの補助を拡充するとともに、私学の財務情報の公開を進めます。
5.誰もが自分らしく生きられる社会
(1)平和の啓発・継承
- 若い世代に向けた発信強化や戦争関連資料の活用、平和記念館の整備など、平和の尊さ、戦争の悲惨さを次世代に継承する取り組みを強化します。
(2)ジェンダー、人権、多様性
- ジェンダーを巡る無意識の偏見を解消するとともに、男女賃金格差の解消、日本的雇用の変革など、性別に因らずキャリア形成できる環境づくりを進めます。また、女性の健康や妊娠、出産に関する相談体制を充実させます。
- ジェンダー平等や多様なSOGIの理解促進、あらゆるヘイトやハラスメントの禁止、差別の解消など、多様性が尊重される社会を実現します。
- 選択的夫婦別姓や同性婚の法制化の早期実現を目指し、実現までは東京都版パートナーシップ制度の拡充を図ります。
(3)障がい・デフリンピック
- 障がいの有無で分け隔てられない社会を目指し、審議会の割り当てなどの見直しで、当事者の意見をより反映させ、インクルーシブ施策を進めます。また、情報・コミュニケーション保障機器の開発支援に加え、デジタル活用を含めた障がい者スポーツの推進などに取り組みます。
- 民間就業支援やチャレンジ雇用の促進、就労移行支援の拡充、デジタル活用や短時間労働の独自支援など、障がい者雇用を拡大させます。
- 特別支援学校の支援員や専門人材、ICT機器や学校設備の充実など、学ぶ環境を整備するとともに、保護者の心身の負担軽減に取り組みます。
- デフ大会に向けた競技環境の整備やライブ配信の実施、交通や観光など聴覚障がい者に配慮した設備の導入支援など、大会を契機に共生社会を加速させます。また、手話言語条例を活用した普及に取り組みます。
(4)スポーツ
- スポハラ根絶に向け、大会のあり方の検討や指導者への啓発をさらに進め、誰もが自分らしくスポーツを楽しみ、続けられる環境を目指します。
- 都立スポーツ施設の充実に加え、企業や大学といった民間施設との連携など、都民がスポーツに親しみやすい環境整備を一層進めます。
6.忖度にまみれた議会・行政を変える
(1)議会・行政改革
- 企業・団体献金は受け取らず、政治資金パーティーも開催しません。政治とカネの問題と決別し、透明で公正な政治を実現します。
- 年4回ではなく、1年365日いつでも仕事に臨むことのできる「通年議会」を導入します。
- 非正規公務員の業務実態を点検するとともに、処遇の改善を進めます。
- 公金支払先情報の公開、随契の検証、行政評価の深化など、都政の透明性や効率性を高めます。
- 事業の検証を重視したPDCAサイクルを確立するとともに、区市町村への権限・財源の積極的な移譲、市民参画の推進など、ボトムアップの行政を推進します。
- 業務のあり方自体を見直すDXの推進を通じ、都民の利便性向上と職員の負担軽減を図ります。
- 市町村の自主性や特殊性に配慮することを前提に、市町村総合交付金を拡充します。